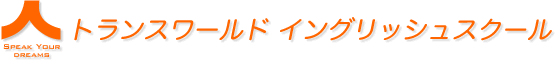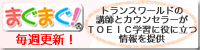|
TOEIC Part 7対策(1)
TOEIC Part 7は「読解力」よりも「情報検索能力」!
皆さんこんにちは。今回から数回に分けて、TOEICのPart7(長文)
対策についてお話したいと思います。
TOEICを受けたことがある方はおわかりだと思いますが、とにかく問題量が多く、
初心者の方はまず全問題を終わらせることが大変ですよね。
参考までに、TOEICのReading Sectionの内訳とおおよその所要時間を確認しておきますと、全100問(75分)のうち、
Part5 短文穴埋め問題 40問 1問30秒=20分
Part6 長文穴埋め問題 12問 1問30秒=6分
Part7 読解問題 48問 1問1分 =48分
(1つの文書:28問、2つの文書:20問) 計74分+誤差1分
となります。
ただし実際には、Part7の問題を1問1分で終わらせるのは至難の業ですから、
なるべくPart5,6で無駄な努力をしない
(わからないものはわからないとあきらめ、サクサク解く)
技術が必要になります。やはりPart7には50分を残したいところです。
そうすると、TOEICが午後1時にスタートする場合、Listening Sectionが
45分ありますから、Readingが始まるのは13時45分からですね。
そしてPart7に50分を残すためには「14時10分」までにはPart5,6を終わらせる
必要があるわけです。
この14時10分というのは重要な時間ですから覚えておいてください。
(※もしTOEICが13時スタートでない場合は終了時刻から50分を引いた時刻を確認しておきましょう)
たとえば実際にTOEICを受ける場合に、Part5,6で25分間だ、なんて意識して問題を
解いても、必死に解いているうちにあと何分あるか、なんてことを考える余裕は
なくなってしまいます。
ですから、14:10という時刻をまず頭に入れておいて、その時刻まであと何分、
という逆算の発想で問題を解いてみてください。
そうすると、タイムリミットまでの時間と、Part5,6で残している問題数が視覚的に
わかりますから、「無駄な努力」をしなくなり、結果Part7に時間を残せることになります。
最悪なのは、特にPart5の短文穴埋め4択問題の、ボキャブラリーを問う問題で、
延々と悩んだ挙句時間を浪費してしまうことです。
単語なんて知らないものは知らないわけですから、
きっぱりとあきらめてその時間をPart7に使う方が有効ですよね?
そのためにもぜひ、「締切時間」14:10を意識して、
この時間までには絶対にPart6まで終わらせるんだということを頭に入れて、
「緊張しながら」問題を解いてください。
さて、いよいよPart7対策ですが、まず学習者の皆さんで誤解が多いのが、
TOEICの長文は、どれだけ文章を読み込めたか、つまり読解能力を問うもので
あるという考えです。
もちろん、英語の文章を読むわけですから、文法力、単語力がある程度必要には
なりますし、実際に単語が解答のKeyになることも多いのですが、
いわゆる大学受験で問われるような「読解問題」ではない、
ということを胸に留めておいてください。
つまり、文章を和訳させる問題であるとか、ましてや書き手の心情を読み取る
問題などは一切出題されないわけで、問われるのはひとつだけ、
設問(question)で問われている情報を本文の中から正確に検索し、
選択肢の情報と照合して判断する能力=「情報検索能力」だとお考えください。
どんなに本文全体を細かく正確に読みこんでも、誰もほめてはくれません。
極端な話、本文の細かい情報までは把握できていなくても、設問で聞かれている
情報が見つかればそれで正解を得られるわけです。
もし皆さんのなかで、過去にTOEICを受けた際に時間が余って仕方がなかった、
暇を持て余したというような方がいれば、今度はすべての文章を正確に読み取る
ことにチャレンジするのもよいでしょう。
でも、そんな人はめったにいませんよね?
たいていの方は全問題が終わらない、あるいは終えるので精一杯という
感じではないでしょうか。そうであるなら、今後は正解を得るための読み方
に変えていく必要があるといえるでしょう。
そこで今回はトランスワールドが提唱している、Part7読解のメソッドを紹介したいと思います。ポイントは、「情報検索能力」ですよ。
Part7の読み方は問題文のテーマによってもやや変わってきますが、基本的には次の3ステップだと思ってください。
<ステップ1>
問題文(本文)の見出し+第1段落の第1文(この最初の1文のことを
Topic Sentenceといいます)を読んで、
「何についての文章であるか(=文章の目的)」を把握する。
<ステップ2>
問題文(本文)の残りをできるだけ時間をかけずに「流し読み」する。
この際、どこにどのような情報・データが記述されているかということ
(アウトライン)を把握する。
<ステップ3>
設問(Question)をよく読んで、問われている情報が何であるかを正確に把握し、
<ステップ2>で確認した情報と照合して、正しい選択肢を決める。
さて、いかがでしょうか。ほとんどの方は読むことに必死になるあまり、
<ステップ2>の本文の読み込みに集中してしまいがちなのですが、
実は重要なのは<ステップ3>の設問の読み込みなんですね。
どんな情報を本文から探せばよいのか、ここにこだわって読んでいかないと、
選択肢に挙がっている単語やフレーズは、すべて本文で使われているものですから、
すべてが正解に見えてしまったり、逆に正解の選択肢なのに、単語が言い換えられて
いる(これをパラフレーズといいます)ために、
正答だと見抜けないということになってしまいます。
ですから何よりも、確実に本文の中に該当箇所をピンポイントで探し当てること
ができるか、ということを肝に銘じて問題を解いてください。
そしておおかた、Part7の問題は「全体を問う問題」と「部分を問う問題」
に分けることができます。
「全体を問う問題」としては、「本文の目的(purpose)は何か」とか、
「main topicは何か」というパターン。
これは<ステップ1>が重要で、英語は結論から書かれますから、
最初の1文(場合によっては最初の2~3文)に注目して、文章のテーマを把握する、
という習慣をつけてください。
「部分を問う問題」としては、具体的な数値であったり、日時、固有名詞
(人物、会社名など)に関するものが多いですから、これは<ステップ2>
で全体を流し読みするときに、だいたいこのあたりにこういった情報が
書かれているな、という程度で、あとで検索しやすいような読み方をする
必要があります。
つまり、1回読んだだけで全体の情報を正確に把握する必要はないわけで、
設問を読んで該当箇所を検索できればいい、ということなんですね。
このアウトラインをつかみながら「薄く読む」技術がなかなか慣れないと
難しいものです。
TOEICは時間との勝負ですから、「情報検索」ということをしっかり意識して、
効率的な読みかたを心がけてください。次回は、テーマ別の攻略法を紹介したいと
思いますのでお楽しみに!
★☆★編集後記★☆★
こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか?暑さもだいぶ和らぎ
空気は秋の香りを含んでいる感じですね。こうなると食欲が俄然湧いてきます!笑
やっぱり秋は秋刀魚ですがこの間塩焼きの鯖を食べたんですが、すごく美味しかった
ですよ!さてさて今回のメルマガ「うーん、なるほど」と思うところがいっぱいあって
参考になりました!皆さんは如何でしたか?是非意識をしてTOEICの時に問題を解くと
良いと思います!但し、やはり基礎的な語彙力や読解力が無ければせっかくの
テクニックも活かせませんから、常日頃から英文に目を通す、読むクセは付けておいて
下さいね!次回のパート7攻略法も気になります!それではまた来週。。。

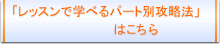
|
 <QRコード>
<QRコード>